「リードマネジメント実践録シリーズ」では、大手コンサルティングファームでマネジャーを務める私が、リードマネジメントの手法を使って2人のシニアコンサルタントの人材育成に試行錯誤する実録をお伝えします。
マネジャーとして部下を育てる立場にいると、
「なぜ自律的に動いてくれないのだろう」
「どうすれば主体的に成長してくれるのだろう」
と悩む場面が少なくありません。
私自身もまさにこの課題に直面しています。任されているのは、2人のシニアコンサルタントの稼働率を確保しつつ、彼らを「小規模案件をリードできる主任」へと育てていくこと。
しかし現実には、細かい指示を出さなければ十分なアウトプットが出てこない、プロジェクト全体を見渡すリーダー的役割を任せきれない……そんなジレンマを感じてきました。
この記事では、そうした私の悩みを率直に共有し、さらに「リードマネジメント」という考え方に出会って実践を始めた経緯をお伝えします。
同じように部下育成に頭を悩ませている管理職の方、そして「上司にどう見られているのか」「どう成長すればいいのか」と模索している部下側の方、どちらにも自己投影して読んでいただける内容になればと思っています。
背景|コンサル業界の人材育成
コンサル業界に「人材育成の文化」は、ほとんど存在しません。
表向きには「研修+OJT」という仕組みが整っているように見えますが、実態は育成どころではなく、案件の成果物をどうにか期限内に仕上げることが最優先。部下の成長に腰を据えて投資する余裕は基本的にありません。
その結果、育成は必然的に「本人任せ」になります。
有能な人材は、多少雑に仕事を振られても勝手に成長していく。一方で伸び悩む人材は、任せにくいという理由で仕事を振られなくなり、成長の機会すら失う。
こうして、「育つ人は勝手に育つ、育たない人は放置されて淘汰される」 という構造が業界に根付いています。
これが、コンサル業界特有の「アップ or アウト」というキャリア文化を生み出しています。
機能しない人材育成 | クライアント案件でOJTの余裕はない
コンサルティング業界の人材育成は「研修+OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」が標準です。入社時や昇進時に研修で基本を学び、その後はプロジェクトの現場で経験を積みながら成長していく――形式上はそうなっています。
しかし、実際のクライアント案件では納期と成果物の品質が最優先で、上司が部下に手取り足取り教える余裕はありません。実際の育成スタイルは 「部分的に仕事を任せ、出来上がった成果物にフィードバックを返す」 という形に落ち着きます。
私自身も、部下に「まずやってみて」と任せ、成果物に赤入れをして返す、というやり取りを繰り返してきました。超有能な部下であれば、これを糧に自力でブラッシュアップし、期待を超える成果に仕上げてくれます。
しかしそうでない場合は、時間切れや品質不足により、最終的には私が修正して完成させざるを得ないことも多い。こうなると部下は「自分で仕上げる機会」を失い、成長のチャンスを逃してしまうのです。
成長できるかどうかは「本人次第」
このような環境では、成長できるかどうかは部下本人に委ねられます。
能力の高い部下は、仕事の与え方が多少雑でも成果を出せるため、次々と新しい仕事を任され、加速度的に成長していきます。
逆に、成果が安定しない部下は「任せにくい」と判断され、難度の高い仕事を振られなくなり、作業や事務処理をこなすだけになっていきます。結果として、ますます成長機会を失っていきます。
行き着く先は「アップ or アウト」
こうした仕組みの積み重ねにより、コンサル業界には「アップ or アウト」という独特のキャリア文化が根付いています。
育つ人は勝手に育ち、そうでない人は淘汰される――。
人材育成の仕組みはあるように見えても、実態としては「育成に力を入れる文化」が乏しく、“本人が勝手に育つかどうか”に委ねられているのが現実です。
課題1|マネジャーとしての私の悩み
人材育成が「本人任せ」である環境の中で、私は特に厄介な課題を抱えています。
それは――“超有能タイプではない2人のシニアコンサルタントの稼働率を確保しつつ、彼らを育成しなければならない” という責任です。
ここでは、私が直面しているこの悩みを整理します。
本人任せでは伸びない2人を育てる責任
コンサル業界では、育成に手間をかけるよりも「既に有能な人材をアサインして成果を出す」方が効率的です。
しかし私は、チームの事情から“放っておいても勝手に育つタイプ”ではない2人のシニアコンサルタント(仮名:アイさんとダンさん)の稼働率を確保する責任を担うことになりました。
やるからには“シニア卒業”まで導きたい
正直に言えば、この責任がなければ、ここまで本気で人材育成に取り組むことはなかったかもしれません。育成は時間も労力もかかり、短期的に成果が見えにくいからです。
それでも任された以上、やらざるを得ない。そして、どうせやるなら彼らをシニアコンサルタントとして“卒業”できるレベルにまで育てたい――そう考えるようになりました。
育成のゴールは主任としての自立
私が描いたゴールは明確です。
- 1年以内に「現場リーダー」としてプロジェクト全体を見渡しながら動けるようにする
- 2年以内には「小規模案件の主任」を任せられる水準に到達させる
この目標を達成できるかどうか。
それこそが、今の私の最大の悩みであり、チャレンジなのです。
課題2|部下(アイさん・ダンさん)の悩み
私が抱えている課題は、マネジャーとしての悩みだけではありません。
部下である2人のシニアコンサルタントにも、それぞれ異なる悩みがあります。彼らの成長を阻んでいる要因を整理してみます。
アイさん:丁寧だが突き抜けない
アイさんは、仕事を進めるうえで慎重に背景を確認し、認識齟齬の少ないアウトプットを出してくれるタイプです。プロジェクトの状況をしっかり共有すれば、現場リーダー的な役割も一定レベルでこなすことができます。
しかし一方で、成果物は「求められた水準を満たす」止まりであり、マネジャーの期待を超えることはほとんどありません。プロジェクト全体を俯瞰する視座もまだ十分とは言えず、主任として任せられる段階には至っていません。
悩みの根本は、「丁寧さはあるが、突出した強みや自走力に欠けること」です。
ダンさん:謙虚だが“作業者”にとどまる
ダンさんは、自分の弱みを理解しており、謙虚な姿勢で仕事に取り組む人物です。感情的になることが少なく、淡々とタスクをこなすことができる点も長所です。特に地道なデータ分析は好きで、腰を据えて作業する力はあります。
ただし、現場リーダー的な役割を担おうとする意識が乏しく、業務を「作業」として受け止めがちです。プロジェクトの背景理解や仮説立案・示唆出しといった上流工程には苦手意識があり、成果物も細かい仕様を詰めて指示しなければ十分な質に到達しません。
悩みの根本は、「作業には強いが、リーダーシップや上流工程の思考に踏み込めないこと」です。
共通する課題:リーダーとしての自律性が不足
2人に共通しているのは、「このままでは小規模案件の主任を任せるには不安が残る」という点です。
- アイさんは“突き抜けない丁寧さ”
- ダンさんは“作業者としての堅実さ”
どちらも長所はあるものの、リーダーとして自律的に動けるレベルにはまだ達していません。
そのため、2人自身も「どうすれば次のステップに進めるのか」という悩みを抱えているのです。
解決策への手がかり|リードマネジメントとの出会い
こうした課題に直面していたとき、偶然手に取った一冊の本がありました。
橋本拓也さんの『部下をもったらいちばん最初に読む本』です。
(Amazonアソシエイトとして適格販売による収益を得ています)
この本の中で紹介されていた「リードマネジメント」という考え方に、私は強い関心を持ちました。
従来のマネジメントが「どうやって部下を動かすか」に重きが置かれるのに対し、リードマネジメントは 「部下が自ら動きたくなるように関わる」 ことを重視します。
これは、まさに私が抱えていた課題――
- アイさんに「もう一段上の主体性」を引き出すこと
- ダンさんに「作業者からリーダーへ踏み出すきっかけ」を与えること
――の解決に通じる可能性があるのではないか、と感じました。
もちろん、本を一読しただけで何かが劇的に変わるわけではありません。ですが、「本人任せでは伸びない2人」に対してどのように関わればよいかの指針が得られたことは、私にとって大きな転機でした。
具体的な実践の中身については、次回以降で詳しくお話しします。
まずは最初の一歩として、週1回15分の1on1をスタートし、2人の“上質世界”を知ることから始めました。
まとめ/次回予告
今回は、コンサル業界における人材育成の実態と、私自身が抱える課題――
- 本人任せでは伸びにくい2人のシニアコンサルタントを育成する責任
- 彼ら自身が抱える「リーダーとしての自律性不足」という共通課題
について率直にお伝えしました。
そんな状況の中で出会ったのが「リードマネジメント」という考え方です。
部下をどう動かすかではなく、部下が自ら動きたくなる関わり方を探る このアプローチに、私は大きな可能性を感じています。
次回は、実際に私が始めた週1回15分の1on1の様子を紹介します。
- 部下の“上質世界”を知るとはどういうことなのか?
- たった15分でどんな気づきが得られるのか?
- そして、最初の面談で見えてきたアイさん・ダンさんの意外な一面とは?
ぜひ次回もお読みください!
参考文献 | 部下をもったらいちばん最初に読む本
今回の記事で紹介した本はこちらです:
(Amazonアソシエイトとして適格販売による収益を得ています)
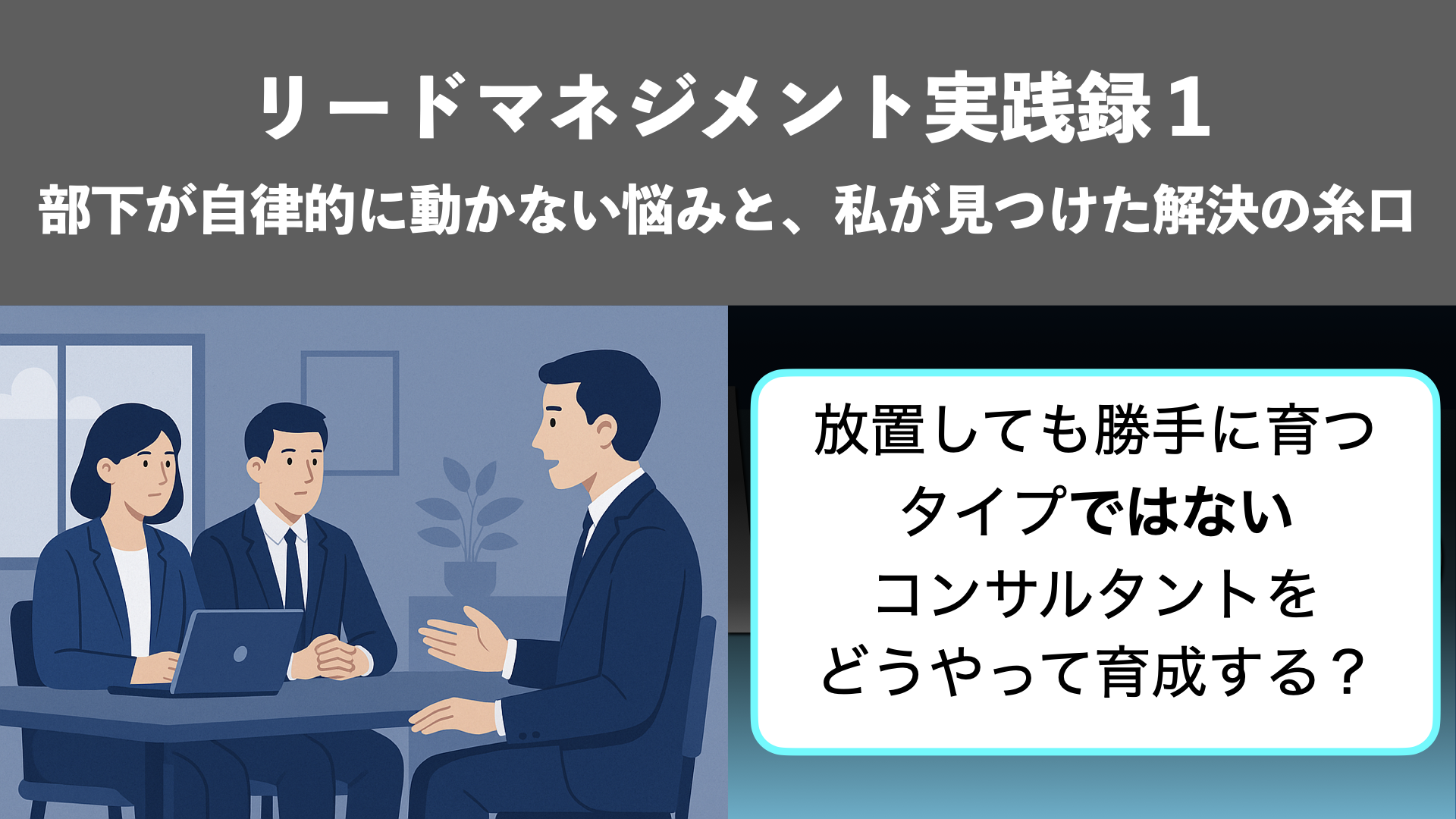
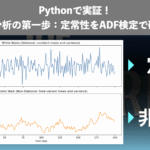
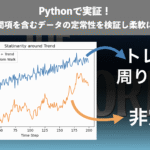
コメント